| 第15回で説明しました湯川秀樹の理論ですが、このπ中間子によって陽子と中性子が結びつけられているという考え方は、他の力にも一般化されてます。
電磁気力が働くということは、そこに電界や磁界が発生してるということなのですが、これを素粒子論的にとらえなおすと、電気や磁気を帯びている物体からは光子が出たり入ったりしていると考えるのです。光子は電磁波ですからとらえ方を変えただけにすぎませんね。さらに、ふたつの電子の間の電気力の働きを、電子の間を光子が交換されるととらえなおすことができます。
この考えはファイマンという人が考えたファイマン図というものを考えるとわかりやすくなります。まっすぐの線が電子、波線が光子を表します。 ファイマン図はいわば相対論のところででてきたミンコフスキー図になっていて、上の方が時間的に未来、下が過去、左右は空間的なへだたりとなっています。ここでひとつ約束があって、粒子の反粒子は時間の向きを逆に書くことになっています。つまり、反粒子というものは未来から過去に向かって移動する粒子と区別がつかないということになります。
素粒子論における、電子-電子の衝突現象は計算がややこしいのですが、一旦ファイマン図を書き下しておいてからそれを数式に置き換えると計算が楽になるのでした。
ところが、ここで困難性が生じました。ファイマン図は一意には書けないのです。その書けたファイマン図の結果を全て足し合わせた結果が衝突現象の結果となるのです。そして、これらの結果を足し合わせていくと無限大が発生するという問題が出てきたのです。イメージとしては電子に近付いていくと電子から発生している光子が、さらに電子対にわかれて、そこからまたさらに光子が発生するという具合になっていて、結局電子の近くには無限大の電子が発生することになってしまい、電子の電荷は無限大になってしまうのです。
その困難性は湯川の同僚である朝永らによって解消されました。くりこみ renormalizeと呼ばれる手法です。計算の途中では無限大が出てくるのですが、ある定式化にのっとって計算するとトータルでは有限な結果が得られるというものです。この方法は絶大な効果を発揮し、こうして計算された結果は実験結果と非常によく合っていました。これは量子電気力学(Quantum
Electro Dinamics =QED)と呼ばれています。
朝永はくりこみ理論の功績で、ノーベル物理学賞を受賞しました。
すぐに、電気力と弱い力が実は似ているということが判明しました。弱い力はW粒子というボソンによって力が媒介されるのですが、普通にファイマン図を書くとひとつの中性子からみっつの粒子が出てくる過程のように見えます。しかしファイマン図を少し書き換えてやると、電子-電子散乱現象と似た形をしていることがわかるのです。 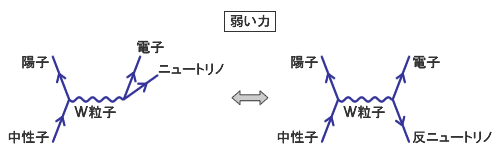
違うところは力のオーダーだけです。
では何故力のオーダーが違うのでしょうか。実はエネルギーのレベルを上げていくと、そのうちふたつの力のオーダーは同じになって区別がつかなくなってしまうのです。つまり、電磁気力と弱い力は統一的にあつかうことができるのです。
この電磁気力と弱い力を統一した理論のことをワインバーグとサラムの電弱理論といいます。
ではこの電弱力と強い力や重力は同じようにして統一することができるのでしょうか。実はそう簡単には行かないのでした。
|
